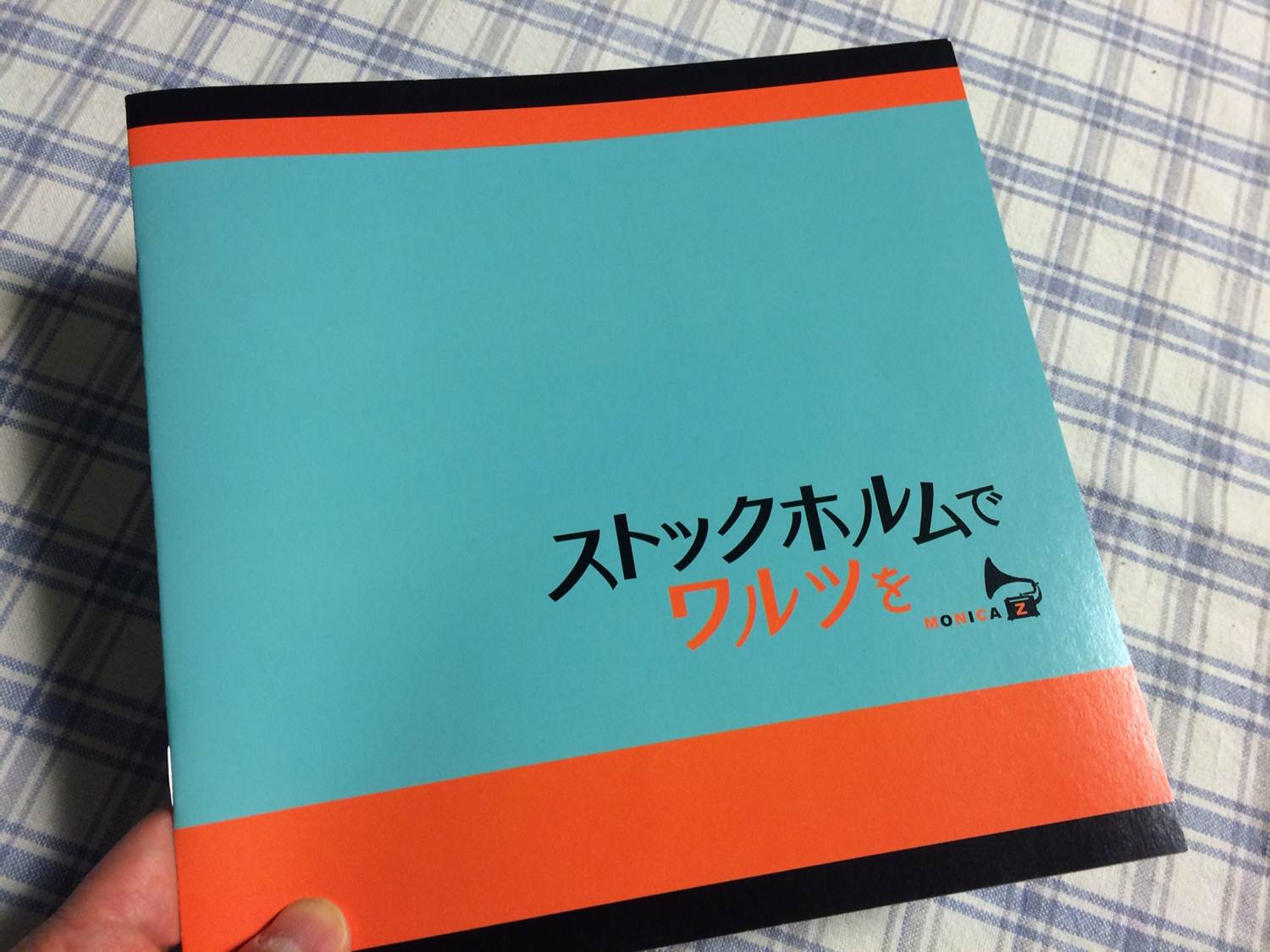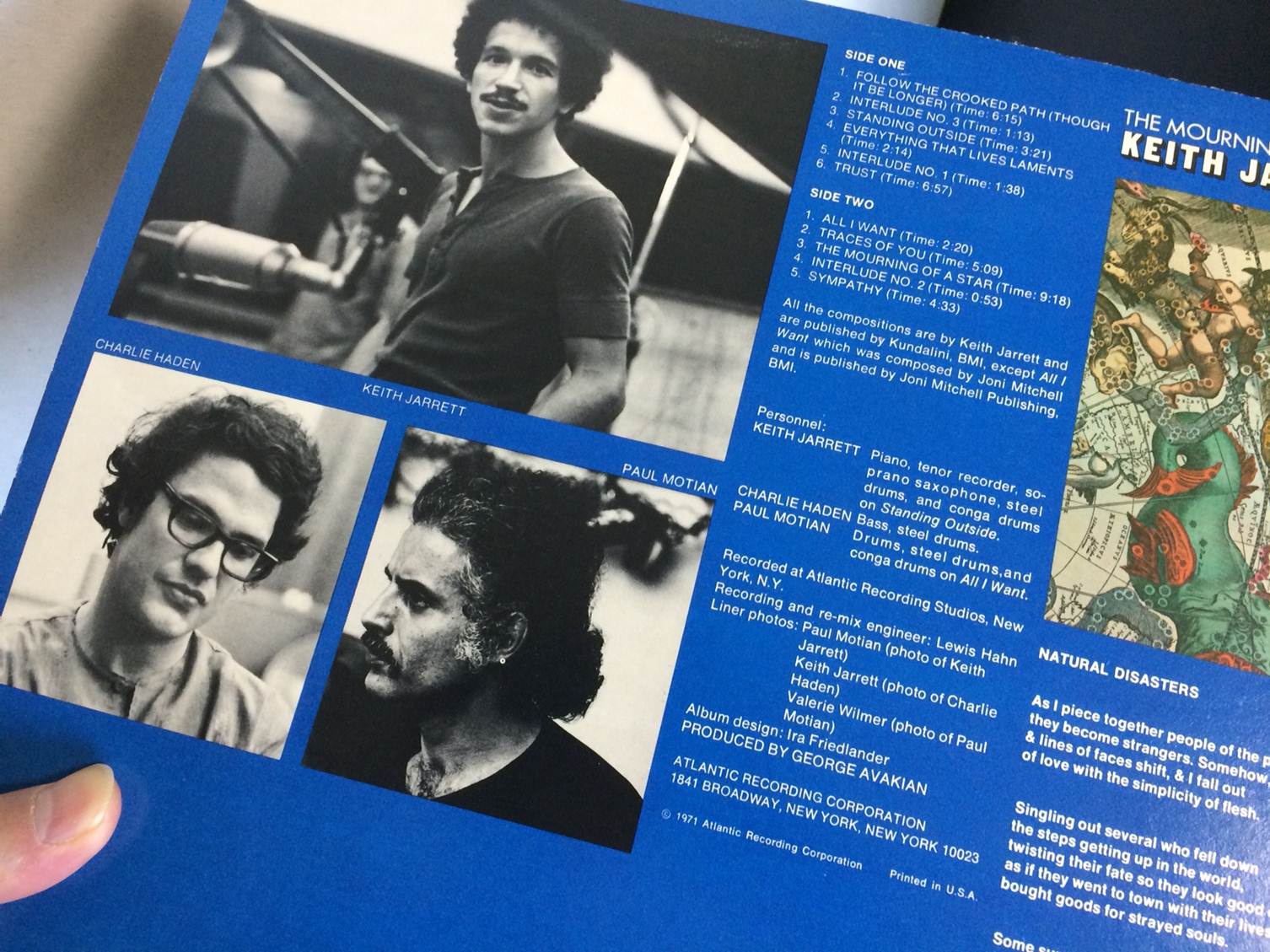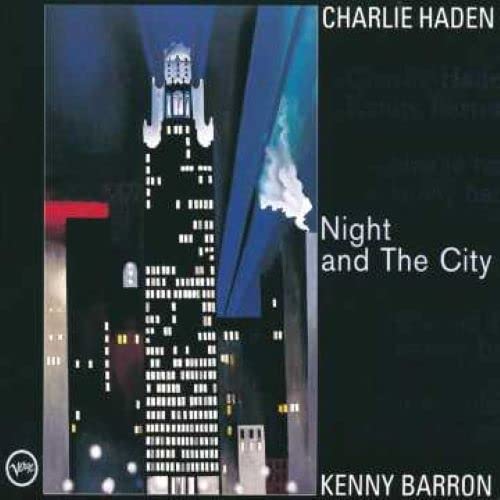もう一年以上前のこと。突然テレビから流れてきたドゥービー・ブラザーズの「What A Fool Believes」を耳にして、不思議な感覚に陥った。目を向けると、キムタクが出てくる車のコマーシャルだったが、あの特徴的で軽快なイントロが30年以上の時を経てとても懐かしいのに、何故か思いっきり新しく感じたのだ。
☆ Link:TOYOTA トヨタウンCM5「ラブ&ジーンズ 市長登場」篇
イントロに続き、わずかに歌が流れただけでCMは終わったが、当然の如く、続きが聴きたい、さらにはこの曲の入ったアルバム 『Minute By Minute』 が久々に聴きたい、となる。とは言っても確かドゥービー・ブラザーズのCDは一枚も持っていなかったはず。でも、聴きたい、聴きたい、聴きた~い...ということで、押入れの中をひっくり返し、ダンボールに詰め込まれていた大量のカセットテープの中から、件の一本を必死のパッチで探し出したのだった(関西ローカルです)。
カセットテープのインデックスカードに書かれている日付は1980年6月30日。確か大学に入って間もない頃、友人の持っていた2枚のドゥービーのアルバムを、カセットテープの両面にそれぞれ録音させてもらったものだ。さて早速、と思って、はたと気づいた。そういえば、息子が使っていたカセット付きのミニコンは、少し前に廃棄したんだっけ。ということで、携帯型のカセットプレイヤーを探し出し、充電をしてインナーフォンを装着、さて聴くぞ、とプレイボタンを押すも、反応なし。回らない。そこに至って初めて、我が家にはカセットテープを聞く手段が、既に消滅していることに気づいたのだった。
その後、聴きたい気持ちはふつふつと燻っていたんだけど、先週になってようやくアルバム 『Minute By Minute』 をCDで買いなおし、懐かしい音楽にどっぷり浸った。
それにしても、ボーカルをとっているマイケル・マクドナルドの声は、いつ聴いてもシビれる。僕の好きな男性ボーカルの声の中でも、間違いなく3本の指に入るだろう。少し高めの、ソウルフルだけど生真面目な感じのハスキーボイス。笑顔なんて似合いそうにないちょっとシリアスなくぐもった声。「What A Fool Believes」は、そんなマイケル・マクドナルドを頂点に引き上げた曲でもあった。
この曲はビルボードチャートでトップになり、1980年のグラミー賞・最優秀レコード賞を獲得、さらに最優秀楽曲賞もとって、この曲を共作したマイケル・マクドナルドとケニー・ロギンスにもスポットが当たった。ただ、日本ではなぜか、その前年にグラミーをとったビリージョエルの「素顔のままで」や、前々年のイーグルス、「ホテル・カリフォルニア」ほどには、流行らなかったと記憶している。
しかし、僕は当時、米国発の音楽を色々追う中で、この曲の影響力の絶大さを目の当たりにした。楽曲の良さもさることながら、スタジオミュージシャンとして長年鳴らしてきたマイケル・マクドナルドが見せるピアノでのこの曲特有の奏法と音形は、その後さまざまな楽曲に飛び火し、そのたびに僕達も面白がって、話題にした。
例えば、ロビー・デュプリーの「Steal Away」。1980年発売のAORの名曲だが、途中、おおっと思うような音形が出てきて思わずうなづいたものだ。
そうそう、ポインター・シスターズの「He’s So Shy」も、ピアノではなかったけど、そのテンポといい、サビの部分の伴奏音形といい、影響を受けてるんだろうな、と感じていた。同じ1980年発売で、ビルボードのチャートでも結構上位まで行ったはずだ。まあここまでくれば、日本でも松田聖子の「白いパラソル」の前奏なんて、グレーゾーンなんだろうけど...
ところで、マイケル・マクドナルドと共作したケニー・ロギンスは、日本ではその5年後の「フットルース」あたりまで、あまり知られてはいなかったけど、やはり同時期の自分のアルバムにこの曲を入れている。これが、ギター主体で、結構雰囲気が違うわけで、やはりマイケル・マクドナルドのあの奏法が、当時のこの曲の決め手だったのかな、という気がする。
35年近く前のこの曲が今でも新鮮に響くのは何故なんだろう。あるいは、当時のことを知っている自分には特別にそう聞こえるだけなのかもしれないと、たまたま帰省していた息子に聞いてみた。彼曰く。「最近の曲かと思った。古く感じない。」ふむふむ。君は正しい!
その要素は色々あるのだろう。今も変わらないピアノの入ったバンド編成と、いい声、コーラスが主体であること...いやいや、編成だけのせいではない。完成されて隙のない独自性のある音楽や演奏は、いつの時代にも、新鮮に響くものなのかもしれないね。
<おまけ>
この曲が流行ってから十数年後、ケニー・ロギンスのライブにマイケル・マクドナルドがゲスト出演した時の「What a Fool Believes」の競演です。ギターを前面に出したケニー・ロギンスバージョンの一端が表現されています。同じ曲とは思えないくらいだけど、これはこれで、結構いけますよね。
<関連アルバム>
上のブログランキングもポチッとお願いします!
![ミニット・バイ・ミニット [紙ジャケット・コレクション~MQA-CD/UHQCDエディション] ミニット・バイ・ミニット [紙ジャケット・コレクション~MQA-CD/UHQCDエディション]](https://m.media-amazon.com/images/I/51d5YBA2NcL._SL500_.jpg)